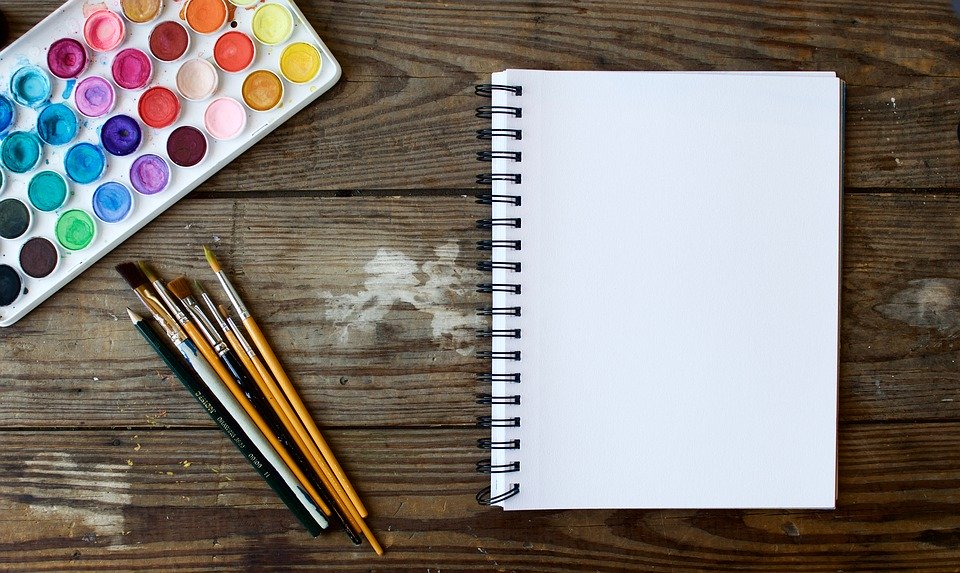行事や水泳指導や、日常特にイベントのない日も含めて、地域(?)の大学から介護等体験を受けるために大学生の方が特別支援学校にやってきます。
実施期間は2日間で、朝から夕刻まで在校して、指導に参加し、清掃や教材づくりなどをしています。今日も何人かの大学生が学年の枠に入ることになったのですが…。
「介護等体験を実施するにあたって」みたいな形で書いて、提出された文章がグサっとささりました。(思わず、これはAIで書いたものじゃ…と勘ぐってしまいましたが)その内容ですが、今もない訳ではないけれど、この仕事を始めた頃に感じたことが列挙されていました。
・障害特性に応じた子どもとのかかわり方を知りたい。
・どこまで支援するか、どこまで主体性を尊重するか考えたい。
これらについて、教員になってしばらく経てば、ある程度の慣れと、型を覚えて応用することでなんとかなってくるのだと思うのですが、それは本当に学生さんに見せられるものか?説明できるものか?というと、ちょっとギョっとなってしまいます。
教員の日常は、すべての子どもに配慮する、視野が狭くなり過ぎない範囲の質を担保する、教育課程(時間割)などを守る、隣の学級などとの協力をする、などが同時に求められています。なので、どこか1つに全振りすることはできません。
なので、ある程度慣れと型でやらないと進められないところがあるのですが、こなすだけ、考えないで自動化してしまう、といったことが続くと、自分の価値観の中で完結してしまったり、実はスキルの精度が少しずつ落ちてしまっていたりすることがあります。
なので、時々、このようなコメントを校外にいる人から、初心にかえる問いや質問を投げかけられることは有意義かも、と思いました。