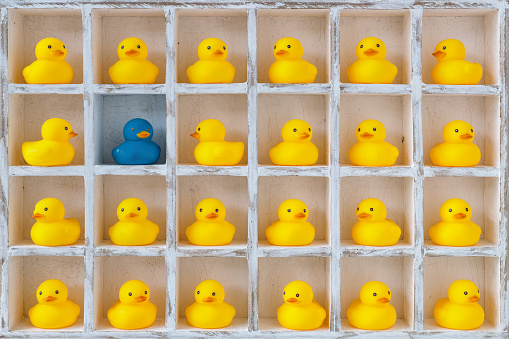文化祭シーズンです。
毎時間、体育館では学部ごと、学年ごとに入れ代わり立ち代わり舞台練習が行われています。
この練習場所と時間の割り振りは校内で取りまとめられ、極力平等になるよう配慮されています。
ちなみにですが、小学部の低学年は午前中の授業と、給食を食べたらすぐに帰ることが多いので、割り振るときはそのような学部ごとの事情を加味して配置する必要があります。
先日、職員室で、舞台上で支援する教員の服装について話がでていました。
以前書いた記事のなかで、教員は黒子だし、目立ってはいけないから「黒」にすべきだ、というルールが存在することについて書きました。今回、話として挙がったのは、以下のようなものでした。
・黒は色として強いから、子どもの副、照明、背景のことを考えたら逆効果だ。
・教員も一緒にいる人として登場させるので、黒子という位置づけでない。
どうでしょう?
子どもが主役、教員は黒子だから目立ってはいけない、だから「黒」、というのは目的と根拠があるとして、教職員集団のなかで当たり前のルールとして存在していました。しかし、今回は黒にしたらどうなるか?、本当にそれが効果のあることなのか?という問いがあり、それをもとに答えがだせたことが大きいと思いました。
【そもそも】
学校で作られるルールは、ルールがない、ルールがないと困る、ということで誰かが1つ旗をあげる、または提案をする。そうすると、それが共通理解されたルールとして、意味も想定される結果も考えずに引き継がれることになります。
これは、自分たちのしていることがどんな意味をもっているか考えない、主体性や専門性がないと指摘されるかもしれないと思います。しかし、外部や保護者から何かを提案されると、頭ごなしに否定せずやってみる、受け入れる、工夫して実施するといった、ある意味、従順さが必要なことがあります。
作業療法士だったとき、「作業療法士として」、「OTとして」どう考えるか?と問われることがありましたが、このように自分の考えや専門性をはっきりしすぎると、他との摩擦や葛藤に苛まれることが増えます。そのため、疑問をもつ、深く考えるといったことをせずに、無難に受け入れていったほうがトラブルになることが少なくなります。