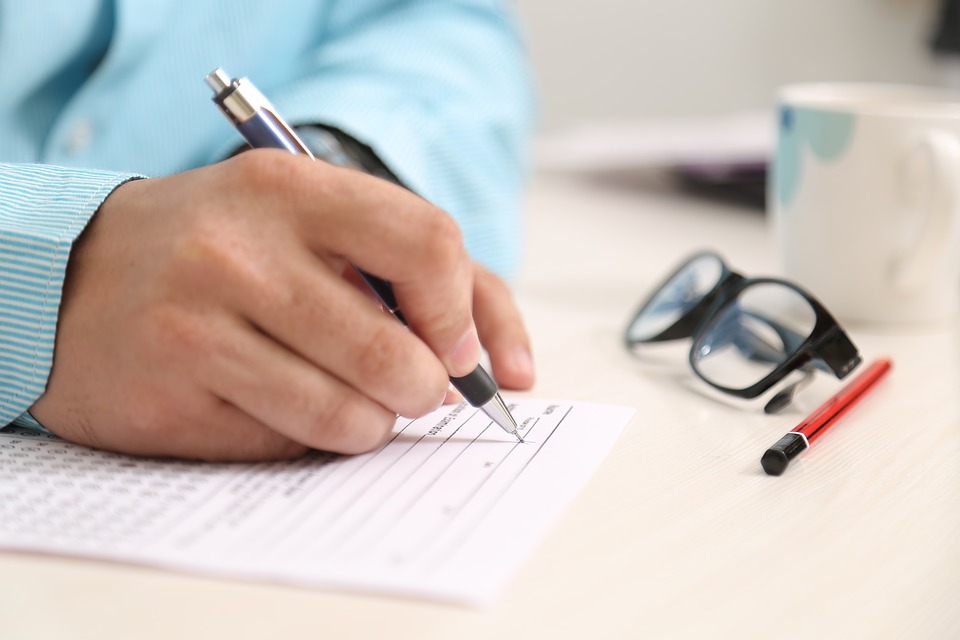保護者へのお願いを書いてみることにしました。
このお願いは、私の教育観や学級の状況、保護者や児童生徒によって、毎年変わるものです。
このようなお願いについて、保護者が「うちの子どもを、ちゃんと指導しろ」とおっしゃっているブーメラン的なもので、「複数の児童生徒を同時にみている訳じゃなく、1人なんだからちゃんとやって」というものと、建て前や文部科学省等がアナウンスしているものと学校の現場が乖離しているために、距離感がはかりにくいでしょうからハッキリ言います、の二つになります。
【身支度はしてきてね】
まず、髪の毛ですが、バサバサと顔にかかるなら結んできてください。また、とれやすい髪留めは止めてください。教員が髪留めの修正に目と手をかけることになり、必要な指導に行きつかないことがあります。また、髪留めなどが無くなると、持ち物の紛失として「すみません」と連絡するハメになります。
また、衣服についてですが、自分としては、集団の場としてどうかと思うような華美なもの、ダジャレの要素が強いもの、露出な多いものなどは求めていません。また、かわいく見える、かっこよく見える、おしゃれに見えるものも、求めていません。
学校では日常生活の指導の目標で、「衣服の着脱」などを挙げていますが、それをする基本は家庭です。前後の分からないトレーナーやズボン、飾りが多くて着替えを放棄して眺めたり、困惑したりしているのですが、それはいいのでしょうか、背中にプリントがあって前面は無地(その逆もあり)、などはどうでしょうか。
子どもは着替えのときに、手順だけでなく上下左右、表裏、ズボンと上着の区別などのタスクをこなしています。その区別する目印をなくして、どうやって服を着るのでしょう。結局、大人が聞いても分からない区別の仕方を説明したり、停滞したり困惑したりするのを見かねて介助しています。
介助になると、子どもが学ぶ機会を奪ってしまいます。そうして、これは自分ができないことで、大人がやってくれることだと思い込むようになり、自分ができること(部分的にでも)が見つからないと自尊心は育ちませんし、依存心が強くなっていきます。
勿論、他者に支援を求める、言葉やサインで伝えることも行いますが、そこは楽して、考えないできりぬけるのではなく、自分はこれができて、これが難しい、難しいことについて支援をもとめる、が基本にあると思います。
個別の事情には配慮しますが、何でも迷ったらお願いすることが習慣になってしまって、介助されないと癇癪を起す児童生徒を担当したことがあります。このケースについて、「できる、できない」以前に、「これはするもの」に変換するために半年近くかかりました。
【決まったことはやる】
歯磨きや服薬など、文書で確認されたもの、依頼に基づいて合意したものは、基本実施しています。事情でできないことがあったときは、謝罪をしたり、連絡をしたりしています。
が、しょっちゅう薬や歯磨きセット、その他必要なものを再三忘れてくるのは困ります。世相もありますが、やることをしなかったというのは許されない風潮があり、学校現場はそれらに対して過度に反応する傾向があります。
「~がないのですがどうしましょう」、「~できませんでした、すみません」と、先生はよく電話連絡しています。
「できないことはできないんだ」、「それは家庭での話であって、学校ではできない」という時代もありました。今ではそれは保護者の意向に沿わない悪だ、傲慢だといった扱いを受けがちですが、社会の中で生きるために、思い通りにいかないこともある、思い通りにいかないときはどうする、といったことも教員に、保護者に、子どもに必要なのではと思います。