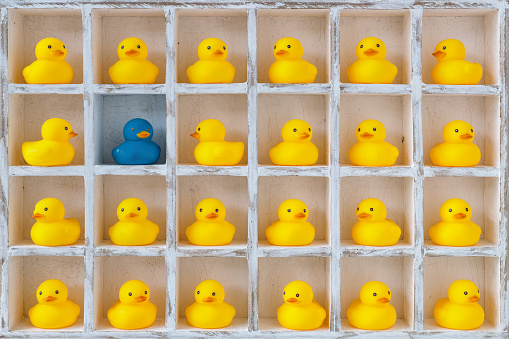作業療法士が特別支援学校に入って、何が役立ったか
学校では、資格があるだけで、その分野のことは何でも知っているという誤解がありました。その点で、養成校時代に「これって使うの?」「これって役立つの?」と思いながらやったことが、断片的に役立ったり、名前を聞いただけでも理解が進んだりして、オールラウンダーなフリができました。
個人的に役立っていると感じたことですが、以下のようなものです。
寝返りから立ち上がり
歩行
整形外科のリハ
関節可動域練習
脳血管障害の方へのリハ
車いすなどの福祉用具の知識
作業分析
運動学
このあたりが役に立っています。
どれも中途半端ですが、それがかえって良かったかもしれません。
もし、奥深くやったことがあったとしたら、それが自分の得意技で、それを活かしたいと思い、何かにつけてそれを使おうとするのではないかと思います。
また、よく言われる「OTとしてどう考えますか?」も消化しないままでした。これも良かったのかもしれません。自部nとしては、資格の種類や縄張りなどはどうでも良く、「役に立てばいい」、「様々なニーズに対応できればいい」といろいろ見て、それをつつき散らかしていたものですから、生活支援の場では大変役立ちました。
寝返りなどは、知的だと動きがどうも変だなと感じた時に、出生後からどのあたりを学び損ねてきたんだろうと考える手掛かりになりますし、肢体では基本的な動作の習得や感覚入力などに役立ちました。
整形外科の知識は、関節可動域いっぱいに動かすことばかりでなく、制限の原因の確認やどこまでならやっていいかの歯止めをかけることに役立ちました。
幅広い知識は仮説と可能性の数を増やし、煮詰まって動けなくなることが少なくします。そうして、もし深い知識と技術が必要なときは、その分野で奥深くやっている人に聞けばいいと思います。
私は普通の教員にはなりきれないし、作業療法士として力量を高めてきた訳ではないから縄張り意識がそれ程強くありません。しかし、普通の教員よりも医療分野の知識がありますし、医療技術者よりも学校の文化や学校生活の支援について知っています。そのため、自分は疎外感を感じることはあっても、劣等感はあまり感じません。この感覚は、実際に学校で仕事をするようになった人なら、「ちょっと分かる~」と感じて頂けるのではないでしょうか。