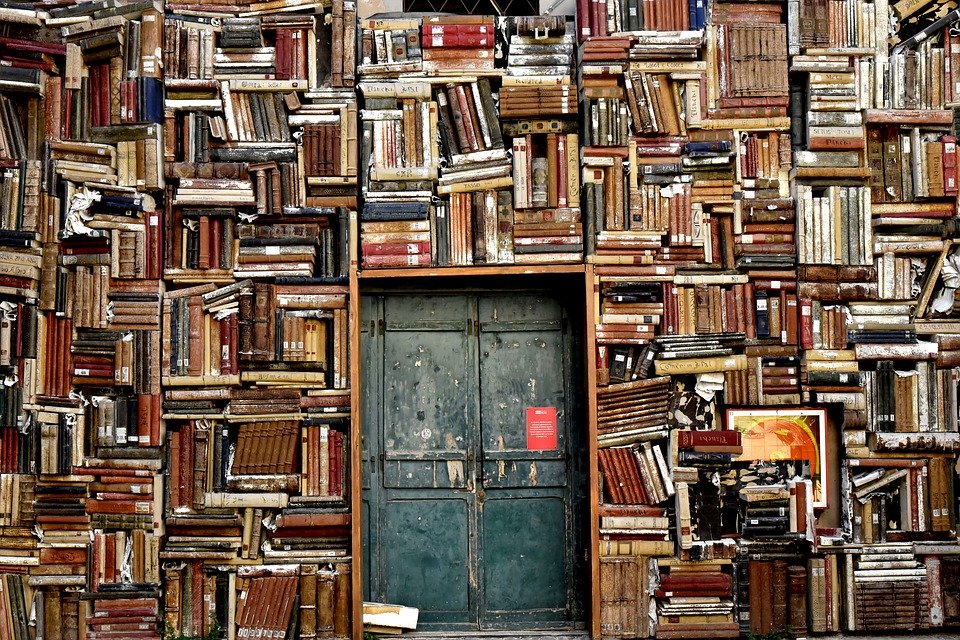夏休みが近くなってきました。
年度はじめから、更新された組織、学年教員メンバーを整えつつ、授業等に追われる日々、やっと落ち着いてきました。
まだ、年度の半分もきていませんが、このあたりで業務分担等の調整や整理を意識しはじめました。特定の人に仕事が偏っていないか、疲れてきている人は誰か、研究授業などの年次研修のペース配分などですが、それに加えて、次年度の学級や学年の運営の準備も考えています。
正直なところ、今年度をもって他の学校に異動してしまう人はさておき、その他の学年の先生が次年度も残る保証はどこにもありません。それでも、同じ学校の中にいるのなら、困ったときに情報収集できる人として役に立ってくれるだろうという感じです。
今年の学年の運営は、選手層に偏りがあり、個々の学級の運営を強く意識するあまり、隣の学級の動きが見えにくい課題があると思われ、次年度にメンバー再編があったとき、大きな穴が空いてしまいます。
【人の動き方の調整】
今の学級経営を捨てる訳にはいきません。それをふまえて、どの学級なら調整できるか、誰を育てるか、どの学級の実態を共有するか考えます。
A先生とB先生がいる4組について、B先生に3組の運営を部分的にでも把握してもらいたいとして…。
3組のどの場面や実態を把握してもらうか
どの時間帯ならB先生が4組を抜けられるか
4組からB先生が抜けた穴を埋めるか
【摂食指導】
学級運営を把握するときにおさえておきたいポイントは
・登下校時の動き
・登下校時の荷物の扱い
・授業時間の合間の過ごし方
・空き時間の過ごし方(ひとり課題の設定など)
・摂食指導
です。このあたりがおさえられていれば、どんな学級に行っても、それなりに過ごすことができます。上記のなかで、ある程度覚えて、一定のパターンをつくれば済むものと、済まないものがあります。
済まないものとして、「摂食指導」が挙げられます。日によってメニューが違いますし、食べ方の成長過程や試行錯誤の日々になっていると、数日見ただけでは把握できないし、理解できないことが多いです。試行錯誤しながら、じっくりつきあって分かってくるものだけに、長期的な指導と観察が必要です。
他の学級の様子を把握するために、人を入れる、入れ替えるのですが、先行投資のために今をおろそかにできないし、今の安定を求めるあまりに、見通しのない行く末をつくってしまうこともできない、といったことを考えると、実は過剰な苦労を背負わされるリスクが激増します。周りなんて気にしない、自分のことをやっていればいいのと割り切っておけば、準備が少なくていい学級にまわしてもらえるので、楽なんです。(ボソ…)