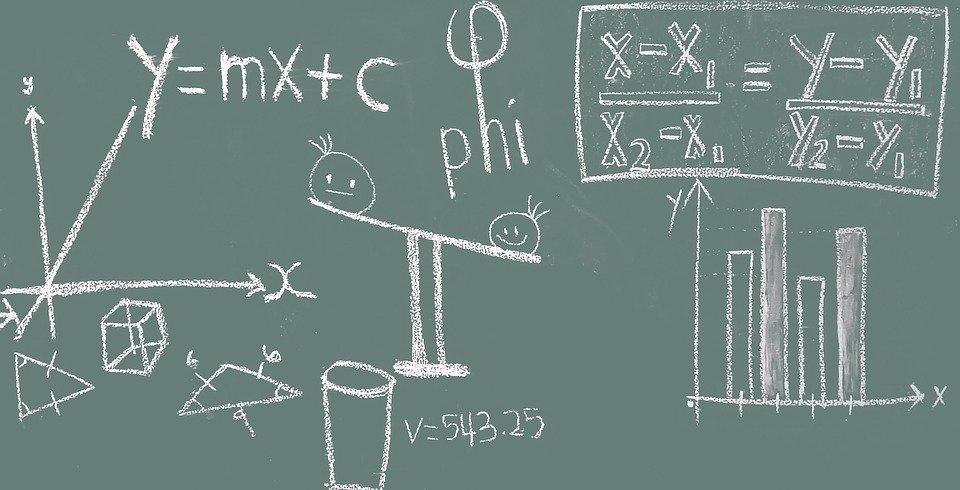麻生副総裁が、「労働」とは、キリスト教の中では罰で、日本書紀などで扱われた労働は善行として扱われている、みたいなことを言っていました。
高市さんが自民党総裁になったときは、「馬車馬のように…」、「ワークライフバランスを捨てます」みたいなことを言っていました。
【教員の労働】
教員の仕事は「これまで」という境界線をつくりにくいもので、かかわるのが人間である以上、杓子定規では済まないところがあり、人情もあろうというところです。
教員の仕事にかかわらず、心身ともにキツいと思うこと、意欲的に取り組めたこと、それぞれたくさんあろうかと思います。自分がこれまでキツいこと感じたことは何なのか、意欲をもって取り組めたことは何なのか考えてみたいと思いました。
【キツいと感じたこと】
職場の方針や大多数の教職員の考え方が自分のものと違い過ぎていて、それに従わなければならないとき
知識や経験を積み重ねることができないとき
自分が積み重ねたことを壊されて、状況が悪化したとき
時間をかけて取り組みたいことに時間がかけられない
意味や価値が理解できないことをさせられる、またそれに時間がとられ過ぎると感じたとき
やっていることが、成果に結びつかないとき
【良かったと思うとき】
自分の思いついたことが、良い結果をもたらしたと感じたとき
成果がでたとき
努力や配慮によって職場環境が良くなったとき
金銭を得た時
自分の知識や経験、専門性が活かされたと実感できたとき
感謝されたとき
自分がやろうと決めた仕事を終わらせることができたとき
【どうだろう?】
仕事について、罰のような苦痛があり、善行を成したときの喜びもあり、だと思います。私も長年仕事をしてきて、ガマンし過ぎるのは心身にとってよくないと思いますし、自分の器にどれくらいまで入るのか分かってきたので、身の丈にあったことをしようと思っています。
教員の仕事について、良いことは確かにあり、やりがい(自分が感じることであって、他人から言われるものでない)もあると思いますが、比較的キツいと思えることが増えてきた気がします。
性格的に自分はどちらかというと、今の時代にもとめられる教員に向いていないのかも、と思います。感情や思考を停止させつつこなす、ある部分知識と経験を使って済ませるだけ、という場面が増えたと感じられ、それらが罰でなく、主体的に行う善行に値するものかと思うのです。
先日、気のない指導や配慮が足りない指導をするということで、経験の浅い先生が注意されているのを耳にしましたが、どこか仕事に対してドライになってしまっているのは自分も同じかもしれないと思いました。